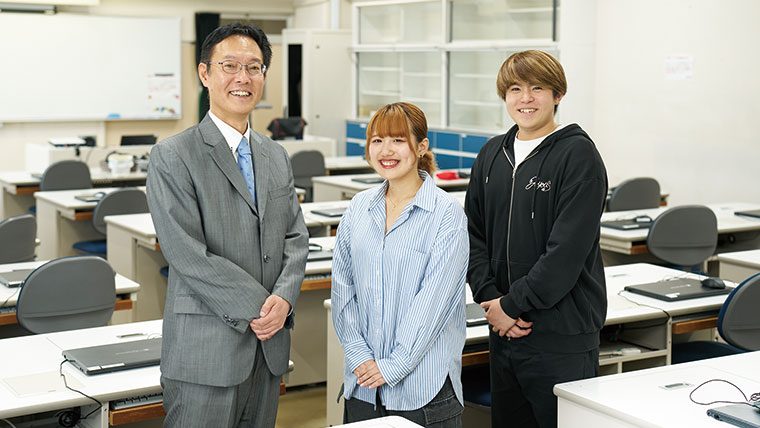入学前から卒業後までの地続きとなる「学び」で、「自ら考え、人や社会のために行動できる」人材育成に取り組む聖学院大学。キャリアデザイン科目の「インターンシップPBL型」(課題解決型)授業もその一つ。同授業は企業から提供された課題に対して学生がその解決策(案)に取り組むもので、昨年度からは地元プロサッカークラブであるRB大宮アルディージャとの産学連携のプロジェクトを実施している。
同授業を担当する基礎総合教育部特任講師の吉川臨太郎先生に、授業の意義や目的についてうかがった。また、昨年度同授業を履修した欧米文化学科(2026年4月より国際文化学科に名称変更予定)3年生の久保田鈴桜さんと、現在履修中の日本文化学科1年生の水野蓮都さんに授業を通して得た気づきや成長の手応えについて語ってもらった。
「インターンシップPBL型」授業は、これからの社会を生きるうえでの素養を身につけるため、学部や学科を超えて学ぶ聖学院エッセンシャルズ科目群のキャリアデザイン科目に位置付けられている。同授業では、昨年、地元のサッカークラブであるRB大宮アルディージャとの産学連携授業が実現。2024年4月から7月までの全15回の授業で、さまざまな学部学科から集まった1年生から4年生の学生24名が「ホームゲームの観客数を増やす」という課題解決に取り組んだ。具体的には、解決のためにフィールドワークを含む情報収集を行い、「スタジアムの一体感を高める」「リピーターを増やす」といったキーワードを設定。実践日となる7月のホームゲームでは、子どもを対象にした「キックターゲット」やスタジアム内を探検する「クイズラリー」、スマホのライトを使った「ライトアップ」の3つのイベントを開催した。
今年度は春学期の授業ではサッカークラブRB大宮アルディージャ、秋学期の授業でバレーボールチームの埼玉上尾メディックスと連携し、それぞれの課題解決に取り組む予定だ。

社会との接点を大切に 将来に向けた「学び」を
授業を担当する吉川臨太郎先生に話を聞いた。
―「インターンシップPBL型」授業の意義について教えてください。
この授業は、企業から提供してもらった課題の解決策をまず学生が考え、プレゼンし、企業側が納得できる内容に仕上げたうえで実践し、最終的に振り返るという流れになっています。その過程で社会人基礎力を身につけ、将来どのような職種に就いても必要とされる、コミュニケーション力や課題解決力といった汎用性のあるスキルを身につけることが狙いです。また、実際に企業の課題に取り組むことで、普段学生が意識することのない受益者意識の醸成や、課題提供企業の業界の仕組みなどを学ぶことも目的としています。さらに本学では、地域と連携しながら学生を育てる人材育成に力を入れており、地元企業と協力した学びを通じて学生が成長することで、地域の活性化にもつながると考えています。
―この授業は大学教育全体の中でどのような位置付けになりますか?
この授業は、高校での探究活動の延長であると同時に、社会ともつながる内容となっており、高校・大学・社会をつなぐ架け橋のような役割を果たしています。本学では「自ら考え、社会や他者のために行動できる人」を育てることを目指し、入学前から卒業後まで一貫した学びの機会を提供しています。この授業は、オープンキャンパスや入試、入学前の事前学習プログラム(PUP)に続いて、入学後の共通教育プログラムの一環として位置づけられており、大学での学びの基盤となるものです。ここで得た気づきや考え方を、学生には自分の専門分野の学びや、将来の社会生活に生かしてほしいと考えています。

―授業で大切にしていることはなんですか。
学生の主体性の芽生えを見逃さないことです。グループでの話し合いの際に、学生から質問が出ることがありますが、学生が自分で考えたり調べたりすべき問題であれば、私から答えは出しません。学生のうちは、まわりの人に助けてもらう立場ですが、社会人になると、今度は自分が誰かの役に立つことが求められます。この授業は「インターンシップ」であるため、学生には社会人としての考え方や行動を意識してもらうことを大切にしています。学生が困ったときには、すぐに答えを教えるのではなく、気づきのきっかけとなるような助言にとどめ、自分で考え、気づくのを待つようにしています。
―昨年と今年の授業を経て、先生の目から見た学生の成長があれば教えてください。
気づきを大切にする学生が増えたと感じています。気づくことで、自分を見つめ直し、成長するきっかけが生まれます。キャリア科目では、今すぐ結果を出すことよりも、将来に向けて力を蓄えていくことを重視しています。だからこそ、この授業では失敗を恐れず挑戦し、その経験から多くを学んでほしいと考えています。
はじめは引っ込み思案な学生でも心配はいりません。本学では、学びや仲間との交流を通じて、自分の新たな可能性に気づき、成長できる環境を提供しています。こうした環境で自分を高めたい高校生の皆さんを、ぜひお待ちしています。
【学生インタビュー】自分を見つめ直し気づきから成長へ
―「インターンシップPBL型」授業を履修した理由を教えてください。

右:久保田鈴桜さん 欧米文化学科 3年
左:水野蓮都さん 日本文化学科 1年
久保田 私は子どものころからダンスをやっていて、将来はダンスイベントなどの企画・開催に関わる仕事をしたいと考えていました。もともとサッカーが好きなこともあり、サッカーの試合という興行について学んでみたいと思ったのが主な理由です。また、私はコミュニケーション能力を高めることを本学での学びの〈マイテーマ〉としていたこともあり、この授業を通して成長したいという気持ちもありました。
水野 1年生のうちから、社会や企業の課題に取り組むことができる点に魅力を感じました。高校生のころは社会と関わる機会がほとんどなかったため、この授業を通して、社会を知っていきたいと考えたのです。
―実際に授業を履修した感想を教えてください。
久保田 事務的なこともふくめ、企画から実施まですべて私たち学生が主体となって取り組んだので、正直、「裏方の仕事はこんなにやることがあるのか」と驚きました。もちろん、大変なだけではなくて、たとえば実践日当日には、キックターゲットが子どもたちに大人気で「楽しかった」と喜んでもらえたり、クイズに参加した観客から「またやってほしい」という声をいただけたりと、「やってよかった!」と思えることがたくさんありました。
水野 今年の授業は今、7回目でちょうど半分あたりです。最初に社会人基礎力について学んだあと、社会人としての視点を意識しながら現地での調査をし、グループごとに考えた解決策を、プレゼンテーションしました。実際に発表をしてみると、根拠が突き詰められていないなど、自分たちの考えの甘さに気づくことができました。反省し、今後に活かしたいと思います。これまでの授業の中では、グループワークでほかの学生と話し合うと自分とは異なるものの見方や価値観を知ることができて、それがとてもおもしろいです。学年や学部学科の枠を超えて履修することができる全学共通科目だからこそ得られる気づきだと思います。
―授業を通して、自分が成長したと感じられることがあれば教えてください。
久保田 初めのころはグループの全員が初対面だったこともあり、私をふくめて全員なかなか意見が出せず、話し合いができませんでした。そこで私が率先して自分の意見を出しつつ、「同じでも違ってもぜひみなさんの意見も言ってほしいです」と司会の役割で呼びかけたところ、少しずつ意見が出てきました。ただ、人前で意見を言うことが苦手という人もいて、「このまま話せる人だけで話し合いを進めてはグループワークにならない」と考えて、SNS上でも話し合う場を設けるなどの工夫をしました。さまざまなやり方でグループみんなとコミュニケーションを取れたこと、自分の得意なこと不得意なことがわかったのが、私にとっての大きな成長だと思います。
水野 今まで自分が目を向けたことがないものに気づくことができました。企業が抱える課題というものは、学生の自分が今まで考えたことがなかったものなので、新たな視点を得ることができ、ものの見方や考えるための姿勢が変化しました。一方で、グループワークを通して、自分の意見に固執しがちという短所に気づくことができました。目標達成のためにはほかの人の意見も取り入れてよりよい意見が出せるようにならないといけないと思うので、今後変わっていきたいです。