金沢工業大学は、2026年度入試(26年4月入学)から総合型選抜に「総合選抜(Uターン型)」を加える。地域活性化のために、当該地域の受験生を育てて戻す入試方式だ。選抜の狙いと特徴について、女子生徒を対象とした「総合選抜(女子奨学生)」と併せて、副学長(入学教育支援担当)を務める青木隆教授に聞いた。

副学長 青木 隆 教授
一般選抜では測れない多様な学生の獲得を目的として、多くの大学が総合型選抜や学校推薦型といった、いわゆる年内入試の拡充を進める。
年内入試の充実は高校生が望むことでもある、大学通信は毎年、進学校の進路指導担当教諭を対象にアンケートを実施している。24年度の結果を振り返ると、アンケート項目の一つ「どういった改革が生徒に受け入れられるのか」の問いに対して、「年内入試の充実」という回答が最も多かった。その背景には、早く進学先を決めたいという思いがあるが、現行の教育課程になり探究学習が活発化する中、その成果を活かしたいと考える高校生も多いのではないか。
他地域からの生徒を育て地元に帰すUターン型
受験生が期待する年内入試について、金沢工業大学は26年度から「総合選抜(Uターン型)」を導入し総合型選抜の充実を図る。対象となるのは、高校時代の探究学習などを通し自分が暮らす地域に対する課題意識を持ち、その解決のために大学で学びたいと考える高校生。青木教授は言う。
「現行の教育課程になり探究学習が活発化しました。そのテーマとして地域の商業や工業、観光などを選択するケースが多く、その延長線上で地元に貢献したいと考える高校生は多くいます。そうした高校生を金沢工業大学で育てて、それぞれの地域に帰して活躍してほしいのです」
近年の高校生は大学選択の際に地元志向が強く、地域の諸問題について課題意識を持っていても、地元の大学で解決法を探ろうという傾向が強いのではないか。もちろん、それでも一定の成果は得られるはずだが、青木教授は、地元を離れて学ぶことの意義について、こう話す。
「出身地を一度離れてみると、視野が広がり客観的な視点で地域の課題をとらえることができます。そこから解決のために何が必要なのかを理解し発想が生まれるのではないでしょうか。題材は地元でも、それを客観的にとらえる時間は絶対に必要です。地元にいると視野狭窄になりがちなのです。腰を落ち着けて学びながら地域の課題について考える高校生にUターン型は合っていると思います」
Uターン型で入学した学生は、出身地域の企業などでインターンシップを実施する。そこで、社会人とのコミュニケーションで得られた地域の課題を大学に持ち帰り、仲間が直面した様々な地域の課題と共に考えることで、出身地の課題を客観的にとらえ幅広い視野が獲得できるという。

学生を育てて帰すベースは金沢工業大学の高い就職力
出身地域でのインターンシップをカリキュラムに組み込める背景には、就職力の高さがある。金沢工業大学の多くの学生が全国の優良企業に就職しており、そこから生まれる多様な企業とのネットワークが地域でのインターンシップを可能にしているのだ。
就職に対するポテンシャルの高さは、多くの進路指導教諭が認めるところ。前述の進路指導担当教諭対象のアンケート項目にある「就職力が高い大学」で常に上位にあり、就職支援を支えるバックグラウンドとなる「面倒見が良い大学」では、20年連続でトップを続けている。
進路指導教諭の評価だけではなく実際の就職率も高い。24年3月卒の実就職率(※)は、97.8%で、卒業生1000人以上の大学のなかで全国4位となっている。この就職力はUターン型に対する期待感を高める。
※実就職率は就職者数÷(卒業生数−大学院進学者数)×100で算出
Uターン型で合格し、入学すると奨学金が給付されるので、他地域からの学生も経済的な負担が小さく学ぶことができる。地元に残ってほしいと考える保護者が増えているが、就職して地元に戻ってくることが保証されており、さらに経済的負担が小さいというのなら、安心して子どもを送り出すことができよう。地域の課題についてしっかりと探究しその成果を客観的な視点でブラッシュアップしたのち、地域で活躍できる人材となって帰ってくるという入試方式は、高校生にとって大きな魅力があるのではないか。
女子の理系進学を後押し 将来の可能性を広げる
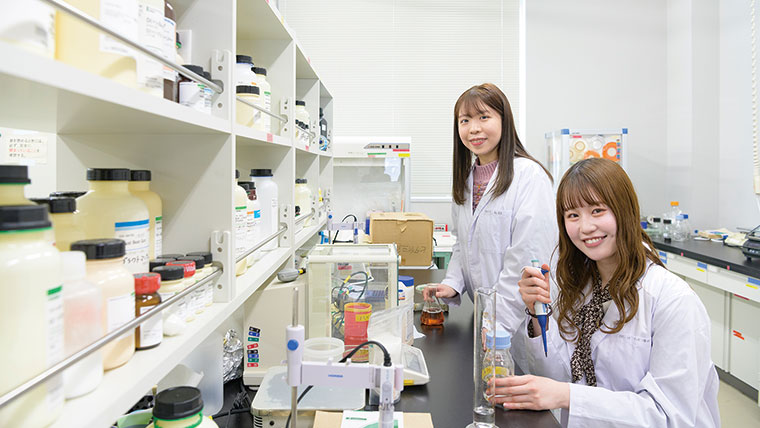
理系人材が不足している日本では、グリーンやデジタルといった成長分野の人材養成に向けた「大学・高専機能強化支援事業」により、理系学部・学科の新設や拡充が進む。理系人材不足という文脈からは、OECD加盟国の中で最下位と言われる理工系学生の女子比率も大きな課題であり、多くの大学が理系学部で「女子枠」を設けている。
こうした状況を背景として、金沢工業大学も25年度入試から「総合選抜(女子奨学生)」を実施している。ただ、その導入理由は、単に女子を増やそうというだけではないようだ。
「女子学生と接していると、『私が男子学生の中に入って、理工系の勉強や研究を進めていいの?』という、いわゆるアンコンシャスバイアスを感じることがあります。そうした思いを払拭して、本人が学びたい学問を選択することが自然な姿だと思います。この入試方式を始めたきっかけの一つに、こうした入試をやらないと、女子を取り巻く状況が変わらないのではないかという危機感がありました。それほど社会の壁は分厚くて高いと思っています」(青木教授)
ただ理系を希望した女性人材を増やし養成するという発想ではなく、その根本にあるアンコンシャスバイアスを取り去ることで、理系分野で活躍できるとあたり前に考える女子を増やしたいという思いが導入の背景にある。
さらに女子のキャリアにおける理系の学問の可能性について、青木教授が言及する。
「社会貢献をしたいと考える女性は多いと思いますが、理系分野を学ぶことでその可能性が大きく広がることを知ってほしい。例えば、看護や社会福祉の分野で活躍したいと思ったら、自ら働く以外に、ロボットやIT環境の構築など、自らやるよりはるかに可能性が広がり、多くの人に自分の思いを提供できるのです。金沢工業大学には、理系の学問をバックグラウンドとして自らの可能性を広げている女子学生が多くいるので、ロールモデルになると思います」
理学や工学系の女子学生比率は年々上がっているが、それでもまだ少ない。女子の理系人材を増やすために、単に入試方式で女子を集めようというのではなく、女子が理系に向かうマインドセットまで考えて実施する金沢工業大学の「総合選抜(女子奨学生)」への期待は高まる。
金沢工業大学は教育目標である「自ら考え行動する創造的探究・実践人材の育成」の達成のため、実社会の課題にチームで取り組み、アイデアの創出から具体化に至る過程を常に意識しながら、自ら考える習慣を徹底的に学ぶ教育を行っている。こうした教育をベースとして、学生の出身地域で活躍するエンジニアの育成や、女子学生に対する教育・研究が進む。「総合選抜(Uターン型)」や「総合選抜(女子奨学生)」は、条件に合致する生徒にぜひ勧めたい入試方式といえよう。

