実践女子大学は、個別支援体制「J-TAS」の活用や1年次からの徹底したキャリア教育に加え、企業や自治体と連携した学びを通して実践力を磨く「社会連携プロジェクト」など、独自のキャリア形成支援を推進。満足度の高い進路選択だけでなく、その先の豊かな人生につながる充実した4年間を学生が過ごせるよう、大学全体で指導・支援を行っている。今回は、入学後からさまざまなプロジェクトに参加し、それぞれが見いだした“なりたい自分”に向かって邁進する2名の学生と、プロジェクトを担当する社会連携推進室長の深澤晶久教授に話を伺った。
社会とつながる経験が、学びへの意欲を刺激する
実践女子大学では、2014年にスタートした「東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト」を契機に、企業や自治体と連携した取り組みを展開し、2021年には社会連携推進室を立ち上げた。2024年度には、企業や自治体との連携実績は学園全体で過去累計705件(2024年度は209件)に上り、2024年度はのべ7,927名の学生・生徒が参加したという。今回話を聞いた文学部国文学科4年の安元彩夏さんと、人間社会学部人間社会学科3年の田中こころさんは、印象に残る授業の一つとして、ともに1年次前期の共通教育科目の「実践プロジェクトa」を挙げた。
「私が一昨年受けた授業では、近畿日本ツーリスト様とサントリーホールディングス様と連携し、企業の方からいただいた課題に取り組みました。企業の方々は私たちを社員と同じように見て対応してくださり、毎回のフィードバックも甘くはありませんでした。入学したばかりの1年生だけで議論を重ね、資料作りからプレゼンまで行うのは相当大変でしたが、あきらめずに取り組めば必ず達成できるということを実感できた授業でした。また、社会に出たときにどのような力が求められるのかを知ることで、大学では自らの意志で学ぶ楽しさに気づき、もっと成長したいと思うようになりました」(田中さん)
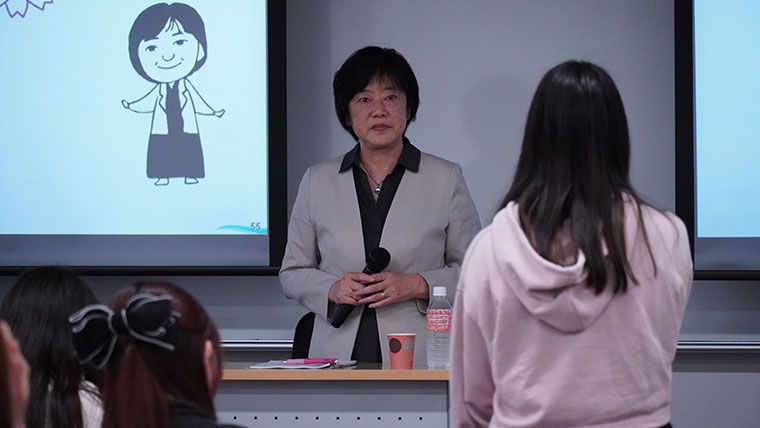
「女性とキャリア形成」の授業にて。実践女子学園木島理事長へ直接質問する学生
一方、安元さんは「実践プロジェクトa」での活動や学びから、自身の視野の狭さに気づいたという。「『実践プロジェクトa』では、自分がいま見ている世界はまだまだ狭いと気づかされ、社会やキャリアについてもっと学びたいと思い、同じく深澤先生が担当されている『女性とキャリア形成』を履修しました。この授業では、企業や組織のトップで活躍する6名の方から、それぞれの生き方、キャリアステップなどについてゲスト自身の体験談を聞くことで、挑戦すること、気になったら一歩を踏み出すことの大切さを知りました」(安元さん)
「『女性とキャリア形成』は、今年で6年目を迎えました。隔週で錚々たる方々にご登壇いただくのですが、お話を聞くだけでは講演会で終わってしまいますから、前後の授業でゲストに関する事前研究と、講演内容の振り返りを行います。授業の進行役は学生が担当し、ゲストの紹介からグループディスカッションのファシリテーション、質疑応答、最後の御礼まで担ってもらいます。加えて、この授業では授業改善のための提案も毎週学生から出してもらうのですが、“授業は誰のためのものか”ということを学生が主体的に考え、席の配置など細かいところから意見を出し合って私とともに改善していくことで、自ずと学生の意欲も高まっていると感じています。主体的に授業に参加する意義を感じてくれていることを実感します」(深澤教授)

文学部国文学科4年 安元 彩夏さん
学部学科や学年を越えて学び合う多彩なプロジェクト
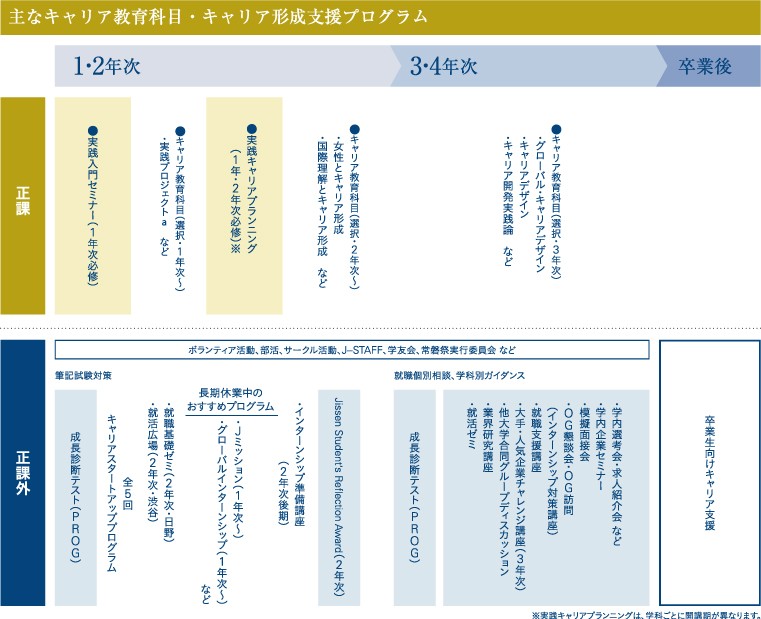
実践女子大学には、こうした学生のやる気に火をつける正課科目に加え、正課外「社会連携プロジェクト」が数多く用意されている。中でも「実践ウェルビーイング・プロジェクト(以下、JWP)」は、正課外であるにもかかわらず多くの学生から支持されている取り組みだ。JWPは「東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト」の次なる取り組みとして、深澤教授が2021年に立ち上げたプロジェクト。「経営」「グローバル」「食」「スポーツ」といったテーマのもと、“Well-being(ウェルビーイング*1)”を考える企画を学生が立て、ゲストを招いて話を聞いたり、体験型のワークショップを行ったりしている。
「“Well-being(ウェルビーイング*1)”はWHOが1946年に提唱し、SDGsのゴール3にも定義され、近年は日本の企業でも人的資本経営やウェルビーイング経営が注目されています。SDGsは2030年をゴールとしていますが、それで取り組みが終わるというわけではありません。“2050年責任世代”となる今の学生たちには、世の中の変化に自分を合わせるのではなく、世の中の変化の一歩先を先導する人になってもらいたいと思い、このプロジェクトを始めました」(深澤教授)
*1:多様な個人が幸せや生きがいを感じるとともに、個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態にあること

人間社会学部人間社会学科3年 田中 こころさん
安元さんと田中さんは1年次からJWPに参加し、今年もメンバーに名を連ねている。
「1年次前期の深澤先生の授業でJWPの案内があり、ぜひ参加してみたいと手を挙げました。単位は与えられない課外活動ですが、私のように『実践プロジェクトa』などの授業で心打たれた学生が、学部や学科、学年を越えて集まっています。企画運営は学生主体で行い、学内だけでなく企業や自治体を訪問することもあります。昨年、私のグループは、EVOL株式会社代表取締役の前野マドカさんを招いて、ウェルビーイングについて学ぶ女子大生フォーラム「What is Well-Being~自分を輝かせるキャリアの描き方2024~」を開催しました」(田中さん)
「私のグループは『エストニアに学ぶウェルビーイング』と題して、ロボット工学分野のスペシャリストを育成するClevon Academy(クレボンアカデミー)のライドー・バルドヴィーさんほか3名のゲストを迎えて、エストニアのソーシャルアントレプレナーシップについて話を伺いました。JWPでの活動を通して、素敵な人生を送るためにはどうしたらいいかを考えるようになり、就職活動もやりたいことや両立させたいことを念頭に置いて取り組みました」(安元さん)

「J-STAFFとして仲間と協力し、来場者に寄り添って学んだこと」と
オープンキャンパスでの経験を振り返り、審査員特別賞を受賞
田中さんは昨年、2年生を対象とした「JISSEN Student’s Reflection Award(以下、JSRA)」で審査員特別賞を受賞した。JSRAは、学生のリフレクションの習慣化と言語化を支援する取り組みとして、2022年度から始まった学内コンペティションだ。一次審査を通過した10名の学生が、最終選考会でこれまでの学習や課外活動などを振り返りながら、自身の成長体験を発表する。田中さんは「J-STAFF」としてオープンキャンパスに参加した経験を取り上げた。
「受験生のとき、私は実践女子大学のオープンキャンパスに3回参加しましたが、ちょっとしか歳の変わらない大学生がこんな活動してるってすごい!かっこいいな!と感動したんです。昨年は一般スタッフとして受験生の質問や悩みに答える『おしゃべりコーナー』を担当しましたが、幹部スタッフとも相談しながら受験生の気持ちに寄り添える対話を心がけました。対応した受験生の1人が、今年の入学式で『合格しました!』と声をかけてくれたときは本当にうれしかったです。自分の経験が誰かの役に立てることを実感しました」(田中さん)
この「J-STAFF」も、同大の代表的な課外活動の一つと言える。一般スタッフをまとめる2年生以上の幹部スタッフは、教職員と連携してオープンキャンパスなどの運営を担っており、安元さんもその一人だ。渋谷キャンパスでは23名の幹部スタッフが活動しているが、学部学科や学年もさまざま。先述したJWPをはじめ、社会連携プロジェクトでつながった学生たちが所属や学年を越えてともに学び合い、切磋琢磨する環境が好循環を生み出している。

文学部国文学科 社会連携推進室長 深澤 晶久教授
プロジェクトで得た知見を、専門の学びやゼミに生かす
これまで、さまざまなキャリア科目やプロジェクトについて紹介してきたが、深澤教授は「あくまでも大学での学びの本質は“学科の専門科目やゼミ”にある」と語る。
「キャリア科目や社会連携プロジェクトは、各学科での専門の学びを補佐するものだと考えています。所属する学科での学びと、それ以外の学びをどう結びつけるかが重要なのです。キャリア科目やプロジェクトで得た知見や経験を、学科での授業やゼミでの活動に結びつけてくれることが理想です」(深澤教授)
安元さんはもともと教員志望で、国語の教員免許が取得できる国文学科で学んでいる。
「大学でさまざまな活動をしてきた中で、やはり挑戦するマインドが芽生えたと思います。今まで興味のなかったことにも取り組むことで、選択肢がさらに広がりました。私は英語があまり得意ではなかったのですが、活動する中で海外への興味が高まり、3年次にはアメリカフロリダ州での「ディズニー・イマジネーション・キャンパス」という『グローバル・インターンシップ』と、『グローバル・キャリアカウンセリング』をきっかけとしたタイでの海外研修に挑戦しました」(安元さん)
安元さんは現在、「中古文学ゼミ」で卒業論文に取り組んでいる。その内容も、日本文学を海外の人々に発信するにはどうしたらよいか?という疑問から考えたという。まだ構想段階ではあるが、「日本の古典における物の怪が海外の人にどのように捉えられるか」について、留学生にも協力してもらいながら進めていくそうだ。
「将来についての意識も変わってきています。教員になりたいと思った理由の一つに、人に影響を与えたいという思いがあったのですが、それは他の仕事でもできることだと気づいたので、今は学校現場だけではなく民間企業などさまざまな可能性を見極めているところです」(安元さん)

タイのスラム街支援を行うドゥアン・プラティープ財団を訪問。
東南アジアの貧困問題について現地の状況を学ぶ
自ら考えて主体的に行動し、社会を変革できる人に
最後に、安元さんと田中さんに実践女子大学のキャリア形成支援について伺った。
「先生や職員の方との距離も近く、ゼミも少人数なので就職活動の相談にも先生が乗ってくださいます。3年次から就職活動が本格的に始まりますが、個別相談やインターンシップ、面接練習などの情報が大学のいろいろなところから送られてきます。また、いわゆるガクチカと言われるような経験も、学内のさまざまなプロジェクトに参加していれば自然と蓄積されていくので、気づいたら手厚く支援されていたという感じです」(安元さん)
「高校の担任の先生からは、大学は自由に自分たちで学ぶ場だと言われていました。もちろん大学では自分が主体的に行動することが大事ですが、実践女子大学は先生や職員の方々が手厚くサポートしてくれる安心感があります。その安心感があるからこそ、私たちはいろいろな活動に参加したいと思えますし、挑戦することにつながっているのだと思います」(田中さん)
深澤教授が着任してから11年、「まなぶとはたらくをつなげること」をキャリア教育の柱にさまざまな取り組みを進めてきた成果が、学生の活躍や進路状況に確実に現れてきているようだ。
「OECD(経済協力開発機構)の『Education2023プロジェクト』において、“エージェンシー(Agency)”という考え方が提案されています。OECDによればこのエージェンシーを『変化を起こすために、自分で目標を設定し、振り返り、責任を持って行動する能力』と定義しています*2。二人を見ていると、自分で考え、主体的に行動し、責任を持って大学や周囲に影響を与えて変革していく、まさに“エージェンシー(Agency)”を実践している人材だと感じます。本学の学生たちは高いポテンシャルを秘めていますから、自らスイッチを入れられる機会をどれだけ提供できるかということが大事ですし、大学全体でそれに取り組んでいると言えるかもしれません。学生はそのきっかけをつかめれば主体的に学び、飛躍的に成長していきます。今後は、安元さんや田中さんのような学生をいかに増やせるかが大切になるでしょう。社会連携プロジェクトは全学共通で開講されていますから、彼女たちのような影響力のある学生を育てていくことで周りの学生たちにも良い影響をもたらし、所属や学年に関係なく、大学全体にウェルビーイングな雰囲気が広がっていくのではないかと期待しています」(深澤教授)
*2:「世界の教育はどこへ向かうか」(中公新書 白井俊著)より引用
実践女子大学は、2024年に創立125年を迎えた。学祖である下田歌子が掲げた「女性が社会を変える、世界を変える」という建学の精神は、時代とともに形を変えながらも、今こそ響く言葉ではないだろうか。2026年4月には食科学部の新設も予定されている。今後も、実践女子大学の新たな取り組みに注目したい。

