社会で即戦力となる理論を基盤とした技術と高い技能を持つ「テクノロジスト」の育成を目指し、2001年に開学したものつくり大学。大学名の「ものつくり」という表記は日本古来の大和言葉に由来するもので、縄文時代からの日本の誇りであるものづくり文化への想いを込めて、初代総長の哲学者・梅原猛氏が命名したものだ。開学以来、優秀な工学系人材を輩出し、多くの卒業生がものづくりの第一線で活躍している。
産業界に求められ、信頼される「テクノロジスト」はどのように育成されるのか。入試課課長の斎藤由匡さんと、同じく入試課職員で同大学卒業生でもある上原苑子さんにお話をうかがった。
―まずは、ものつくり大学とはどのような大学であるのか。その概要から教えてください。
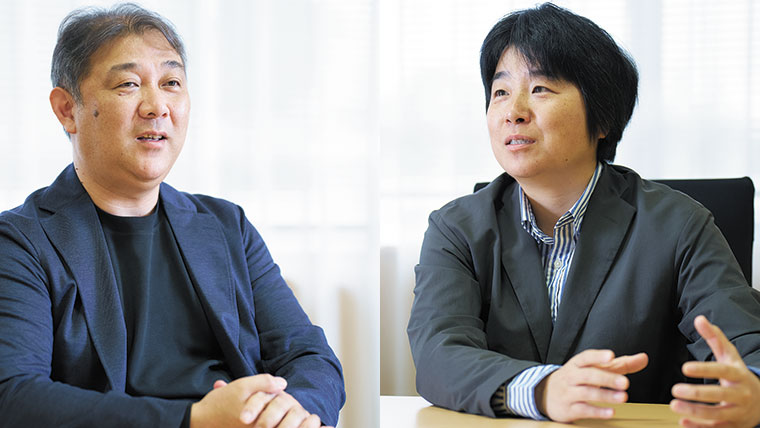
左:斎藤由匡さん 入試課課長
右:上原苑子さん 入試課 入試第一係長
斎藤 本学は大学名にある通り、まさにものづくりに特化した工科系大学です。情報メカトロニクス学科と建設学科の2学科があり、2年次の後半からはさらに8コースに分かれ、少人数教育で専門性の高い技能習得や研究に打ち込みます。クォータ(4学期)制で、横断的で幅広い授業が履修できるため、学生の求める将来像にマッチした知識や技能が身につけられます。
―カリキュラムにはどのような特色がありますか?
上原 徹底した実技・実務教育を軸にしています。1年次から実習が始まり、1クォータ毎にさまざまな分野の実習を経験します。4、5名の班で大きな制作物に取り組むことも多く、全員が役割分担をしつつ制作に携わることで、ものづくりの知識や技術はもちろん、進行管理やコミュニケーションといった社会人に必要な基礎力も身につきます。
多くの理工系大学では1、2年生の間は座学で数学や物理を学ぶことが多いですが、本学ではまず実習によって数式や理論がものづくりの現場でどのように活用されるのかを理解したうえで学んでいく流れとなっています。中高では数学や物理が苦手だったという学生も、実習による体験とひもづくことで数学や物理が学びやすくなるようです。
キャリア教育を充実させるインターンシップ制度
―インターンシップを正規科目に取り入れているそうですね。
上原 本学のインターンシップは、将来を見据えたキャリアアップ教育として位置付けられています。2年次の基礎インターンシップでは、学生の希望業界の受け入れ企業に40日間通って研修を行います。将来進みたい業界の現場を深く知ることで、「やりたい」と意欲を高める学生もいれば、「ちがう分野に進みたい」と考える学生もいます。ここでの気づきを得て、専門コースを確定できるのは大きなメリットですね。また、4年次の専門インターンシップでは、大学で身につけた技能を把握し、就職後のビジョンを描きます。現場を経験することで学生は不安なく就職できますし、企業側もミスマッチのない人材を迎えることができます。こうした充実したインターンシップ制度が、本学の就職率が非常に高い要因となっていると思います。
―就職率が非常に高いだけでなく、就職後の評価も高いそうですが、その理由はなんでしょうか。
斎藤 幅広い分野の実習を経験することで、自身の専門分野以外も基礎的な技術を学び、総合的なものづくりの知見を持っているのが、本学の学生の大きな強みです。大企業ほど業務は細分化されるため、自分の部署以外については知らないケースが多いですが、例えば車であればエンジンなどの構造から組み立てに至るまで総合的に把握している人材は貴重です。また、中小企業ではより総合的な知識と技術が求められ、特に管理や監督、プロジェクトのリーダーといった役職を務めるには欠かせません。4年間の実習や長期インターンシップを通して得た実践経験も、リーダーに相応しい思考力や判断力、協働する能力を養っていると思います。実際、入社して早々にプロジェクトを任されることも多いと聞いています。
上原 学内企業説明会には、230社以上の企業に参加していただくのですが例年非常に多くの企業が「ぜひものつくり大学で学んだ学生に来てもらいたい」という熱意を持って参加してくださっています。企業側スタッフとして本学の卒業生が参加することも多く、本音で話し合いができるなど学生にとっても有益な機会となっています。単なる「就職率」だけでなく、学生が希望する企業に就職できる就職満足度の高い大学であることが、本学の教育力の確かさや就職支援体制の充実の裏付けとなっています。

社会を支える誇りと自負がもの大生の精神
―貴学が学びの中で大切にされているのは、どのようなことでしょうか。
斎藤 実寸大での「本物」のものづくりです。1年生がつくる木製のベンチはキャンパス内や近隣の公園などに設置され、実際に使用しています。ほかにも小屋やオブジェ、大きなものでは製造棟と建設棟を結ぶ橋も設計から施工まで数代かけて学生がつくったものです。また、校舎の外壁やクロス張りも学生が実習や研究を兼ねてリニューアル工事をしています。あるものを利用し資材を無駄にしないという利点もあります。もちろんすべて専門家の指導を受け、安全性と実用性の高いものづくりの学びとしています。
上原 ものづくりの技能を持つ人間としての誇りでしょうか。大学のカリキュラムとは少し逸れるのですが、東日本大震災の発生後、「ものづくりを学んだ自分たちにできることがある」と卒業生が先陣を切って現地のボランティアに駆けつけて片付けなどの作業を行い、その後も多くの卒業生や学生が継続して現地での仮設住宅の修繕などに取り組みました。私は同窓会の役員を務めているのですが、本学の学生には、社会のインフラを支え復興に貢献する「もの大生としての精神」が息づいているように感じます。
―最後に高校生に向けてのメッセージをお願いします。
斎藤 本学はざっくばらんに言えば「変わった大学」です。入学時から幅広いものづくりの実技を経験し、インターンシップで現場を知り、専門コースを決めてからはひたすら実技と研究に取り組んでいく。こんな大学ほかにはないでしょう。だからこそ、ものづくりが好きな学生ばかりが集まり、生き生きと学んでいます。実技先行なので、理数科目に自信のない文系の高校生でも、ものづくりが好きなら大丈夫です。興味を持ったら、ぜひ一度オープンキャンパスで、本学の授業やものづくりを体験してみてください。

作品づくりにも挑戦できる体験型オープンキャンパス!
ものつくり大学のオープンキャンパスでは、多彩なものづくりの魅力や社会的意義を高校生に伝えるために、模擬授業や公開講座、ワークショップなど毎回さまざまな切り口の企画を準備している。特に夏休みには、楽器などのつくった作品を持ち帰ることができる「ものづくり特化型オープンキャンパス」(8/10)やロボットアームの操作など学科にちなんだテーマに取り組む「工学探究ワークショップ」(7/20、8/24)など、体験型のオープンキャンパスが開催される予定だ。
詳しくはこちら https://www.iot.ac.jp/entrance/opencampus/


