9つの学部・学環で約9,000人の学生が学ぶ甲南大学。文理両領域の学部を有する総合大学であると同時に、学生同士や学生と教員が身近に交流し融合できるキャンパスサイズであることから、「ミディアムサイズの総合大学」を標榜している。同大学は、その特性を生かして多様な学びときめ細かな指導を展開し、学生1人ひとりの可能性を伸ばす教育を実践。2026年度からは「進化型理系構想」のもと、理系3学部で新たな取り組みがスタートする。その狙いや中身について、理工学部の池田茂教授に話を聞いた。
―進化型理系構想の概要と、取り組みの背景をお教えください。

理工学部機能分子化学科
池田 茂 教授
本学には理工学部、知能情報学部、フロンティアサイエンス学部という3つの理系学部があります。このうち、理工学部の物理学科を宇宙理学・量子物理工学科(※)に、機能分子化学科を物質化学科(※)にリニューアルします。また、新たに環境・エネルギー工学科(※)を設置。既存の生物学科と合わせて4学科体制にすることが大きなポイントです。
※設置構想中で変更される場合があります。
大学院教育においては、2026年4月に自然科学研究科のなかに環境・エネルギー工学専攻(※)を設置します。2028年4月には、現在の自然科学研究科知能情報学専攻を知能情報学研究科(※)として独立させます。
施設面では、岡本キャンパスの西・北校地に新理系棟を建築中です。こちらは2027年の完成を予定しています。(※)
進化型理系構想の狙いは、高い成長性と人材ニーズが見込まれている分野での研究・教育活動を強化することです。今、社会から大きな注目を集めて人材育成への期待が高まっているのが、GX(Green Transformation)、DX(Digital Transformation)、マテリアル、新素材・機能性材料、宇宙・量子技術、そして生命科学(バイオ)といった領域です。このうち、バイオについては、理工学部生物学科とフロンティアサイエンス学部において、いち早く先端的な教育・研究に取り組んできました。一方で、GX、DX、マテリアル、新素材・機能性材料、宇宙・量子技術の各分野では、さらなる展開と人材育成が求められており、これに応えるために学部・学科の改編を進めています。こうした中、GXおよびマテリアル分野における教育・研究体制の強化を担う新たな学科として設置するのが、環境・エネルギー工学科です。
―環境・エネルギー工学科とはどのような学科なのでしょうか。
学びや研究の対象となるのは、再生可能エネルギー、蓄電池、水素、カーボンニュートラルなど、GXの実現に貢献する技術です。これらのテーマに対して、材料科学(マテリアルサイエンス)の視点からアプローチします。環境問題やエネルギー問題に対して、マテリアルサイエンスによって解決策を提示しようという学科です。
―環境・エネルギー工学科のカリキュラムの特色をお教えください。
化学、物理、地学、数学・情報を幅広く学ぶことが特色です。私たちはこれら4つの分野を、「つくる(化学)」「はかる(物理)」「つかう(地学)」「考える(数学・情報)」と位置付けています。
「つくる」とは新たな材料を合成することです。ここには当然、化学の知識が必要です。合成した材料は、性質や働きを調べる必要があります。このとき必要になるのが、物理の知識です。GXに貢献できる材料を開発するためには、地球規模で直面している環境課題や資源の制約を正しく理解することが欠かせません。そのため、地球の構造や変動、資源の分布や循環といった視点から地球科学(地学)を学び、マテリアルサイエンスの知見と結びつけていくことが重要になります。さらに、現代のサイエンスにはデータの活用が欠かせません。効果的なアプローチを予測したりするために、数学・情報の知識が役立つのです。
理学が物事の本質を探究することに軸足を置いていることに対して、工学はアウトプットを重視します。「環境問題・エネルギー問題に解決策を」と掲げる以上、取り組みに必要な科学的基盤を幅広く身につけることが不可欠です。本学科では、化学・物理・地学・情報(数学)の4分野を、1年次の基礎段階だけでなく、3・4年次の発展段階においても継続的に学べるカリキュラムを構築しており、これが大きな特徴のひとつとなっています。
―池田先生をはじめ、環境・エネルギー工学科の先生方の主な研究内容をお教えください。
クリーンなエネルギー源として水素は大きな注目を集めています。しかし、水素の製造にはエネルギーが必要であり、その供給源が化石燃料であれば、二酸化炭素を排出するという本末転倒な状況に陥りかねません。こうした課題を解決する手段として、私が取り組んでいるのが「水を太陽光で分解して水素を得る」光触媒技術の研究です。光触媒となる材料の合成には化学の知識が不可欠ですが、合成した材料の性質を調べるには物理、理論的な予測にはデータサイエンスの力が必要です。また、研究の意義や方向性を考えるうえで、地球規模の視点を持つ地球科学(地学)の知識も重要な役割を果たします。
電池材料研究室の町田信也教授は、二次電池、すなわち充電して繰り返し使える電池の材料を研究しています。次世代の電池として注目される「全固体電池」が町田教授の研究テーマで、電解質に液体を使わず、固体材料で構成させることで、従来の電池に比べて高い安全性と長寿命が期待されています。
有機化学が専門の木本篤志教授(有機電子材料研究室)は、有機材料で太陽電池や有機ELなどの電子デバイスを作る技術を研究しています。
界面物理化学研究室の山本雅博教授が専門とするのは、雨水や海水といった自然水のpHを正確に測定する技術の研究です。雨水は電解質がほとんど含まれておらず、海水は逆に高濃度の電解質(塩)を含んでいるため、いずれもイオンの動きや電極反応に影響を及ぼし、pH測定が非常に難しいという共通の課題があります。山本教授は、そうした複雑な系でも正確に酸性度を評価するための測定手法や原理の解明に取り組んでいます。
地学が専門である地球科学研究室の小荒井千人准教授は、化石や岩石、地層などから古環境を読み取り、現在までの変遷を解明することで、未来の地球環境を予測する研究を行っています。
また、新たに学外から着任予定の3名の教員は、それぞれ先端的な研究に取り組まれています。たとえば、「都市鉱山」と呼ばれる使用済み電子機器などから貴金属資源を効率よく回収するための分子材料の開発、データ科学や計算科学を活用して材料設計を行う研究、さらには光や熱を電気エネルギーへと変換する新しい半導体材料の研究など、多様なアプローチでマテリアルサイエンスの最前線に挑まれています。
―環境・エネルギー工学科での学びを通して、どのような力が身につくでしょうか。
まずは、理系の専門職人材として活躍するためのベースとなる化学、物理、地学、数学・情報の知識です。また、ディスカッションやプレゼンテーションといった研究者、ひいては社会人に欠かすことができない力も養うことができます。本学科では、専門分野の異なる教員が連携して共同研究も行います。ここに学生も参加することで、チームで協働する力を身につけることができます。これもまた、社会で必須となる力です。
理工学部は文系学部と同じ岡本キャンパスにあります。文系学部の学生と教養科目を一緒に履修したり、同じサークルで活動したりと、交流の機会が豊富です。学生数もちょうどいい規模感のため、学生同士や学生と教員、さらに教員同士も連携が生まれやすいです。これらの環境が、協働する力を養う土壌になっています。
―地域社会や産業界との連携についてお教えください。
これまでにも、本学ではGXに関連する企業との共同研究を積極的に進めており、環境・エネルギー分野に関する実践的な学びの場の構築を目指してきました。また、GXとは別に、本学の文系教員と企業が連携し、機能性食品としてのチョコレートの開発に取り組むなど、文理融合型の研究も展開されています。こうした企業との連携実績を背景に、環境・エネルギー工学科では、PBL(Pro-ject-Based Learning:課題解決型学習)を新たに導入し、GXなどの社会課題に対して、企業と連携しながら学生が主体的に取り組む教育プログラムを展開していきます。
また、新たに着任を予定している3名の教員はいずれも、産学連携や社会実装に深く関わる実践的な研究を展開されています。一人は、自身で開発した材料を実際に社会実装することに成功し、その成果は現在も実用化の現場で活用されています。別の教員は、その技術力と専門性を基にベンチャー企業を立ち上げ、産業界との連携を通じて新たな価値創出に取り組まれています。そしてもう一人の教員は、スーパーコンピュータ「富岳」を活用した材料開発に関する複数の国家プロジェクトを推進しており、最先端の計算科学によるマテリアル設計に貢献しています。
研究者は、ともすれば研究室や大学という限られた世界だけにこもりがちです。しかし、イノベーションを起こしていくには「外の人」とのコミュニケーションが欠かせません。社会人として必要なチームで協働する力を養うためにも、学外の人と関わることは大いに役に立ちます。地域や産業界との連携を通して、学生には自分とは異なる新しい価値観に出会い、視野を広げてもらいたいと考えています。
―卒業後に想定される進路をお教えください。
環境・エネルギー分野は、今後の社会を支える重要な領域であり、卒業後の進路も幅広く広がっています。例えば、二次電池のような蓄電デバイス関連の分野は、産業界との結びつきが非常に強く、企業からは即戦力となる人材が強く求められています。実際に、卒業生が電池材料や関連部品メーカーに就職し、研究開発や評価業務に携わっている例もあります。また、さらに高度な専門性を身につけるために大学院へ進学し、産業界やアカデミアでの研究職を目指す学生も多くなると想定されます。材料開発から実用化・社会実装までを視野に入れた実践的な学びを通じて、多様な進路選択が可能な学科です。
―2027年には新理系棟が完成します。

4階建ての建物で、そのうち3階と4階が環境・エネルギー工学科の専有フロアになります。研究室が1か所に集まることで、教員間の連携が今以上に活発になると期待しています。1・2階は学生が誰でも使うことができる共有フロアになります。学生同士や学生と教員との交流の場になり、新たなアイデアがこの場所から生まれてくることが楽しみです。また、ガラス張りで研究中の様子をつぶさに見ることができる「プロジェクト研究室」も共有フロアに設置します。低学年次の学生が気軽に研究の様子を見ることができる環境にすることで、自分の興味と出会ったり、「研究とはどのようなことをしているのか」をイメージするきっかけになってほしいと考えています。
理系棟は、理系学部の校舎がある岡本キャンパス西・北校地に誕生します。既存の2つの棟と新棟は渡り廊下でつながります。その中核となる新棟は、いわば理系学生の「ハブ」となる場所。学部を問わず多くの理系学生が集い、刺激し合う場となるでしょう。
―大学院も新たな体制になります。
企業や研究機関などで研究者や技術者として活躍するためには、大学院での学びと研究の経験が重要になります。そこで、環境・エネルギー工学科が開設する2026年4月にタイミングを合わせて、自然科学研究科環境・エネルギー工学専攻を新設します。大学院生数(定員)は2026年度は修士課程3人、博士課程1人を予定しており、その4年後の2030年度には修士課程10人、博士課程2人まで規模を拡大する計画です。
大学院では、自分自身で課題を設定し、調査と分析を行うという、まさに研究の日々を過ごします。これは私自身の経験から感じていることですが、どっぷりと研究に浸ることができるのは大学院生の間だけです。たとえ研究職に就いたとしても社会に出ると、予算をはじめとした研究以外のことにも労力を割かざるを得なくなります。研究に没頭できるという大学院の最大の魅力を、ぜひ体験してもらいたいです。
実際の研究では、思っていたような結果が出ないことがほとんどです。そのときに、「うまくいかなかった」とネガティブにとらえるか、「思ってもみなかったおもしろい結果と出会えた」とポジティブにとらえるかは、積み重なると大きな違いを生みます。著名な研究者や社会にインパクトを与える研究を行っている人には、後者のタイプが多いように思います。私は、大学院で研究と向かい合う日々を過ごすことを通じて、後者のようなポジティブなマインドを養ってほしいと思って指導に当たっています。そのマインドはきっと、大学院を修了後に高度理系人材として活躍するための力になるはずです。
―どのような高校生に、環境・エネルギー工学科を目指してもらいたいでしょうか。
カーボンニュートラルの実現に貢献したい、地球環境やエネルギーの問題を科学と技術の立場から解決したい、あるいはそのような仕事を糧として生きていきたい人です。化学、物理、地学、数学・情報という4分野を学ぶことが本学科の特色ですが、入学時点ですべての分野を得意である必要はありません。不得意分野があっても、1年次からの基礎的な学びでしっかりと土台を築くことができます。環境問題、エネルギー問題に対する興味を大切にして、ためらわずにチャレンジしてください。
―高校の先生方や受験生にメッセージをお願いします。
理工学部の各学科は1学年40〜45人と小規模です。学生同士のつながりが密で、コミュニケーションを取りやすい環境のため、安心して学ぶことができるはずです。他大学の先生からは、「甲南大学の先生は実験が上手だ」と言われることがしばしばあります。それはきっと、小規模ゆえに学生と教員との距離が近く、しっかりとコミュニケーションを図ることができているからだと思います。
甲南大学というと、もしかすると「文系の大学」というイメージがあるかもしれません。しかし本学における理系教育の歴史は、1951年に設置された文理学部にまでさかのぼります。豊富な実績と培ってきたノウハウをもとに、私たちは社会で即戦力として活躍できる理系人材を育成します。進化した甲南大学の理系学部にご期待ください。
進化は理系の全方位へ!知能情報学部・フロンティアサイエンス学部のチャレンジ
知能情報学部 生成AIで学園創立者を再現。入学式で祝辞を送る

知能情報学部 学部長
北村達也 教授
知能情報学部では進化型理系構想の先陣を切る取り組みとして、2024年4月に「デジタルツイン研究所」を開設しました。本研究所は、AI・VR・ロボット研究を行う「未来創造型研究」と、運送業界の人手不足という社会課題に解決策を提案すべく輸送経路の最適化などの研究を行う「社会実装型研究」の2種類の研究を行っています。
2024年度は未来創造型研究において、甲南学園の創立者である平生釟三郎を生成AIを活用してVRで再現する「AIバーチャル平生」という取り組みを行いました。顔つきや体格、服装などのビジュアルは平生の銅像や写真から再現。私が担当した音声については記録がまったく残っていなかったため、平生に直接指導を受けたOBに聞き取り調査を行って再現しました。AIバーチャル平生が話す内容は、平生が残した日記などをAIに学習させました。こうして完成したAIバーチャル平生は、2024年度の卒業式と2025年度の入学式に登場。学生に祝辞を送りました。
プロジェクトは本学部の教員が「開発者」として参画。それぞれの専門分野を受け持ち、大学院生や学部生も巻き込みながら進められました。わずか1年でAIバーチャル平生を完成させることは非常に困難を伴ったのですが、その姿を学生たちに見せること自体が大変有意義でした。教員であっても試行錯誤の連続であり、他分野の専門家と協働してプロジェクトを進めているという、研究者や開発者のリアルな姿を見せることができたからです。教員にとってもスキルアップや情報交換の場となりました。2025年度は「ロボット平生を開発しよう」という声も上がっています。
2028年度からは、大学院の課程を自然科学研究科から独立させ、知能情報研究科を立ち上げます。組織の立ち位置が学内外からより明確に見えるようになることや定員が拡大するという変化に伴い、さらに研究力が高まるものと期待しています。
知能情報学部では、6つのコースを興味に応じて横断的に学ぶことが可能で、多彩なフィールドで活躍できる力を磨くことができます。ロボット製作に取り組む「AI学びロボットプロジェクト」やプログラミングコンテストなどに挑む「KONANスーパーIT人材育成プロジェクト」など、高度なチャレンジが行える環境も用意されており、これらのプロジェクトには1年次から参加できます。
情報学は今、間違いなく最もダイナミックでおもしろい時代を迎えています。AIは単なるブームではなく、インフラになろうとしています。その大きな盛り上がりの中に入り、新しいものを作り出したいという意欲や興味のある人は、ぜひ本学部でともに学びましょう。
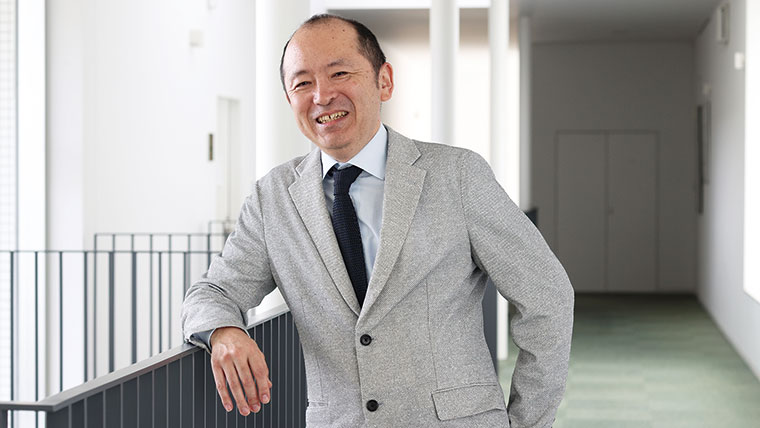
フロンティアサイエンス学部 創薬、医療、先端材料、食品・化粧品という4つのサブコースを設置

ロンティアサイエンス学部 学部長
中野修一 教授
生物学と化学の融合分野を幅広く学びながら、医療をはじめ食品、新素材の開発など多彩な分野に貢献することを目指すのが、フロンティアサイエンス学部です。
本学部では2026年度から、「研究開発リーダー養成プログラム」を開始します。学部のキャンパスは、先進的な取り組みを行う医療機関や研究機関、企業が集積するポートアイランド(神戸医療産業都市)にあります。この立地を活かし、近隣の企業・団体の研究者と交流を行ったり、研究発表などの活動を後押しするのが研究開発リーダー養成プログラムです。プログラムには2年生から参加可能。低学年次に企業・団体との交流を通して視野を広げ、将来の進路選択を後押しします。プログラムは正課の活動でもあるので単位として認定されます。
同じく2026年度からは、研究開発職を目指す先進科学コースにおいて、創薬、医療、先端材料、食品・化粧品という4つのサブコースを設置します。これは、従来の開講科目を整理・再編成したもの。サブコースを選択することで、従来にも増して、興味や目標に応じた効果的・体系的な学びが可能になります。
フロンティアサイエンス学部は、研究開発職に就く高度理系人材の要請をという社会の期待と、「研究がしたい。研究者になりたい」という学生のニーズに応えるべく誕生した学部です。そのような経緯もあり、1年次から実験の授業がふんだんに行われることが特色です。学生は講義形式の授業だけではなく、実際に手を動かすことで理解を深めていきます。実験はまた、自身の興味がどこにあるかを知ったり、将来の自分自身の姿を具体的にイメージしたりして、卒業研究のテーマ選びにも役立っています。
研究開発リーダー養成プログラムの例からもわかるように、企業や研究機関が集積する神戸医療産業都市に立地していることも本学部の大きな強みです。学生が企業や研究機関を訪問して現場見学を行ったり、近隣企業・団体の研究者が講師を務めるセミナーがキャンパスで開かれる機会も豊富です。そこで得たつながりがインターンシップや就職につながったという卒業生も少なくありません。
本学部は幅広い学びを展開しています。それは、大学で学びながら、興味や目標を見つけられるという意味でもあります。「今はまだ将来の進路を決められない」という人にも、本学部を目指してもらいたいです。女子学生が多いことや、少人数制で学生同士や学生と教員との距離が近いことも特色です。安心して学ぶことができる本学部で、思う存分、サイエンスの楽しさを味わってください。


