昭和女子大学が総合情報学部※を新設
昭和女子大学では、2026年4月に「総合情報学部」(※)を新設する。同学部では、データサイエンスに関する学びに加え、これまでの教育・研究で蓄積してきた得意分野の「ビジネス」「健康」「心理」の3つの専門分野を学ぶ、文理融合型のカリキュラムを展開する予定だ。今回は、新学部準備室長の山中健太郎教授と、全学共通教育センターの木村琢磨教授に、学びの概要や育成したい人物像などについて伺った。
※設置認可申請中であり、内容が変更となる場合があります。
3つのドメインを軸に学ぶ文理融合型カリキュラム

山中健太郎
食健康科学部教授。新学部準備室長。博士(教育学)。東京大学教育学部体育学健康教育学科を卒業後、同大学院教育学研究科総合教育科学専攻身体教育学コース博士課程修了。昭和女子大学生活科学部健康デザイン学科准教授、同教授などを経て、2021年より食健康科学部健康デザイン学科教授。専門は身体教育学、スポーツ科学、栄養学、健康科学など。
―総合情報学部の概要についてお聞かせください。
木村 総合情報学部は「データサイエンス」と「デジタルイノベーション」の2学科を配し、デジタルスキルを社会の現場で生かすために、学科共通で「ビジネス」「健康」「心理」の3つのドメイン(分野)を設けます。データサイエンスの手法やデジタル技術と、各ドメインに関する専門知識を掛け合わせた「文理融合型」のカリキュラムが特徴で、現実の課題に対応し、新たな価値を創出できる実践力を養います。
データサイエンス学科では、AIや統計学の知識を活用してデータを分析し、因果関係を読み解く力や、図表やグラフなどを使ってわかりやすく伝える力を磨きます。単にデータ分析をするだけではなく、分析結果を生かした提案ができる人材を目指します。
デジタルイノベーション学科では、AIやVRなどの最新技術を活用した新製品やサービスの開発、企業での業務革新など、デジタル技術を現場での実務に応用できる力を養います。
両学科ともに重視するのは「社会とのつながり」です。ここで3つのドメイン知識を学ぶことが大きな役割を果たします。例えば、企業の人事部でのデジタル活用を考える場合、人事部が抱える課題や実務に関する知識がなければふさわしい提案をすることはできません。そこで、データ分析やデジタル技術の専門知識に加えて、「ビジネス」のドメイン知識を学ぶことが重要になるのです。
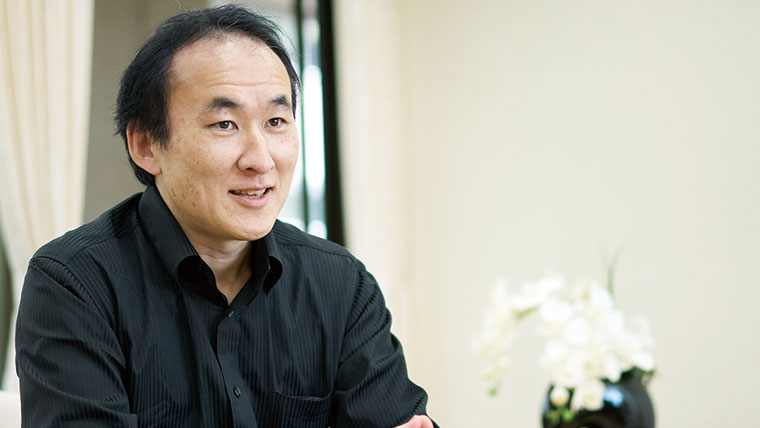
木村琢磨
全学共通教育センター教授。博士(経済学)。スタートアップ企業や法政大学などを経て現職。専門は組織行動論、組織アナリティクス。組織行動・人材マネジメントの理論と統計分析・機械学習およびインタビュー等の定性的分析を組み合わせた研究を行い、2025年、国際的な名誉協会Sigma Xi(The Scientific Research Honor Society、科学研究名誉協会)の正会員に選出。
山中 「ビジネス」のドメインでは、企業の仕組みや経営学などを学びます。「健康」「心理」のドメインでは、食事や運動、心のケアなどに関する知識を修得します。3つのドメインを通して社会の構造や考え方などを理解することで、学んだデジタル技術や分析したデータを実社会に生かすことができ、理論だけでは終わらない実践的な取り組みが可能になります。
木村 さらに、「チームマネジメント」や「プロジェクトマネジメント」といったソフトスキルを育む科目を用意します。これらの授業では、複数の人と役割を分担しながらプロジェクトを進め、リーダーとして全体をまとめるための協働力を身につけます。また、デジタル技術だけでなく、企業文化や倫理的な側面にも配慮しながら課題を発見し、解決策を考える力も養います。理系と文系双方の力をバランスよく育てることで、現代社会の複雑な問題にも柔軟に対応できる人材の育成を目指します。
女子総合大学として蓄積したリソースを生かす
―学内外での連携についてはいかがでしょうか。
山中 本学にはビジネスデザイン学科や食健康科学部、心理学科などがあり、これまで蓄積してきたリソースを生かせることも強みです。これら学部学科の教員や学生との連携も可能ですし、産学官連携による「プロジェクト型学修」では、他学部の学生とチームを組んで企業の課題解決に取り組む実践的な授業を行っていきます。また、本学の海外キャンパス「昭和ボストン」での「サマーセッション」にも、新たなプログラムを計画しています。米・ボストンには教育研究機関やデジタル分野における先進企業が多くあり、学生には将来の可能性が世界にも広がりうることを感じてほしいと思っています。デジタルに強くなろうとする学生の意欲は、2022年度に全学で導入した「データサイエンス副専攻プログラム」に対する需要の大きさからも実感しています。
木村 副専攻プログラムでは、「データサイエンス入門」という基礎的な講義科目から、レベル別の演習科目までを用意し、履修者は入門科目だけで毎年数百人を数えます。実践的なデータ分析技術を用いて学ぶ演習科目も、意欲ある学生たちが学部学科を問わず履修しています。
―入試についてはいかがでしょうか。
山中 入試では数学を必須にしない予定です。ただし、入学後は数学を含め、データサイエンスを専門的に学ぶ土台となる科目についてはしっかり学習してもらうことになります。
木村 さまざまな理由から数学を避けてしまう受験生もいますが、本学部で求められるのは、入試で出されるような複雑な問題を解く力ではなく、数学的な考え方を理解する力です。私は文系出身ですが、研究を通して数学的な考え方とその有用性を理解していますので、これらを学生に伝えながら指導していく方針です。例えば、「生成AIには高校で学ぶ三角関数が使われている」など、数学がどのように生かされているのかが具体的にわかれば、学生も納得感を持って学ぶことに楽しみを見いだせるのではないでしょうか。
山中 入試の数学は正解を出さなければいけませんが、今は数学的な考え方を理解した上でプログラミングができれば、あとはコンピュータが正解を出してくれる時代です。ただし、人間が指示を間違えるとコンピュータは正確な答えを出してくれませんから、数学的な考え方や知識が大事になるのです。
デジタル技術の修得は多分野での活躍に直結する
―想定される卒業後の進路についてお聞かせください。
木村 今やあらゆるフィールドでデータ分析やデジタル技術が必要とされていますので、「IT企業のデータサイエンティスト」のような特定の業種・職種だけを想定しているわけではありません。人事やマーケティング、営業、製品開発など多職種でスキルを生かせますし、金融、ゲーム、フィットネス、ファッションなど幅広い業界でデジタル技術の応用が進んでいます。
山中 もはや“エンジニアにおまかせ”という時代ではなく、どんな職種でもデジタルに強いスタッフがいると業務が円滑に進みます。ベンチャー企業や中小企業で一人何役もこなすような環境なら、なおさら活躍の場は広がりますし、どのような場でもスキルを発揮できる人材の育成を目指しています。
―最後に、受験生や進路指導の先生方へメッセージをお願いします。
木村 データサイエンス学科は、思い込みを捨て、エビデンスに基づいた社会のリアルを知りたいという人、デジタルイノベーション学科は、新しいものを作りたい、もっと便利にしたいという意欲のある人にお勧めします。デジタル技術を生かす仕事がしたい人はもちろん、大学で勉強したいことがまだ決まっていない人や、数学が苦手でデジタル系学部を選択肢から外してしまった人にもぜひご検討いただきたいですね。
山中 現時点では明確な意欲がなくても、何か社会に役立つことがしたいという人や、普段使っているアプリの仕組みを知りたいという人も大歓迎です。自分の興味や関心に沿って専門性を高めることができ、将来どんな分野に進んでも役に立つ考え方やスキルが身につきますので、多くの受験生がチャレンジしてくれることを願っています。


