大学の使命として地域社会に優秀な人材を多く輩出することが挙げられる。それには入学後の教育体制も重要だが、各受験生の志や特性を大学が正確に見極めて評価することが重要である。高崎商科大学(TUC)はこの点を重視して、各選抜制度が受験生の何を評価するかが明確な入試改革を発表した。
「勉学を頑張った人を評価する」4科目型選抜
多くの科目を長期間真剣に学習することは、基礎学力向上だけでなく、幅広い知識や教養、論理的思考と共に粘り強い忍耐力の修得にもつながる。この修得は受験や大学生活のみならず、社会人としても有効であることは明白だ。TUCはこの点を重視。「一生懸命努力して、頑張って勉強してきた人が報われる」入試として、一般選抜・共通テスト利用選抜とも敢えて科目数を増やした4科目型選抜を導入する。入試改革を推進した高崎商科大学事務局次長の鈴木洋文氏は、「この地にある大学として群馬県や高崎市といった地域に、優秀な人材を絶えず輩出していくのは当然のミッションです。そのためにも、少子化だからと受験生に迎合するのではなく、王道である科目主体の入試にも一定のハードルを課すべきだと考えています。地方私大が入試で科目数を増やすことはチャレンジングなことかもしれません。しかし、安易に大学進学が可能になる入試制度がある中、高校生活で本当に学業を頑張った人を評価したい、一生懸命やった人に報いたいという大学の姿勢としても導入すべきだと判断しました」と語る。
選抜制度の特徴としては一般選抜の英語は外部試験スコアをみなし得点として換算することがある。また一般・共通テスト利用とも4科目型出願をすると自動的に3・2科目型の判定対象にもなるので、TUC合格のチャンスも自動的に拡大される。

高校での様々な経験を評価する多様な選抜制度
学力評価の一方で、商業科など専門高校での学びや、学業以外で努力を重ねた活動評価の入試制度も必要だ。また、入試は各大学のポリシーが反映されているべきであろう。今回TUCが発表した多様な選抜制度の幾つかも紹介しよう。
①簿記の力を最大限活用する「簿記会計活用制選抜」*会計学科のポリシー入試
商業高校で履修できる「簿記」は、商学部をはじめとして大学入学後に学ぶ科目であり、公認会計士などを目指す人には必須教科だ。TUCは昨年まで協定校制の学校推薦型選抜「Haul-A入試」を実施していたが、2026年度より簿記を学習するすべての高校生を対象とし日本商業教育振興会の推薦と日商簿記2級合格を軸に、特待制度を含む日商振セレクション選抜制度とする。
「普通科と商業科では教育課程が違います。商業科の生徒が個別学力検査に向いているかと聞かれれば、それは疑問です。先にも述べたように、一生懸命に努力した人が報われるためには、総合型選抜や推薦型選抜も重要な入試区分。特に簿記は商業科では中心となる学問です。高校時代の努力が最大限に評価される入試として本制度の対象は簿記を学習するすべての高校生へと拡大しました。」
と鈴木氏は説明する。公認会計士受験の学習環境に優れ、伝統的に多くの合格者を輩出しているTUC。簿記を学ぶことに高い意欲を持つ生徒には向いている制度だろう。

②ブレスト入試の狙い*経営学科のポリシー入試
ブレインストーミング(ブレスト)は教育現場より、むしろ一般社会において効率よい意志共有や意見交換の場として活用されている。有効なブレストには単なる知識力や思考力などだけでなく、主体性を持ち、多様な人々と協働する高いコミュニケーション力も要求される。このブレストを活用したTUCの探究・ブレスト型選抜の狙いは、主体性や協調性、コミュニケーション力を見る他にも重要な視点がある。鈴木氏は「高校教育は大学受験のためだけに学ぶ場ではないでしょう。大学入試は到達点ではなく通過点です。高校と大学教育を通じて、社会で生きる力を伸ばすことは理想的。そう考えたとき、入試にはマッチングの観点が必要だと思いました。ブレスト入試は入学後の本学の学問にフィットした人材の発見と育成を目的としています。」と語る。高校-大学-社会を1本の「線」としてつなげたいという、壮大な教育への思いが込められた入試制度だ。
選抜は受験生3~4人によるグループワーク形式だ。テーマに沿って互いにアイデアを出し合う形式で、アイデアを出す方法を会得するためにブレストカードを用いるなど通常の試験とは全く異なる。この入試は受験生の育成も目的としており、別の観点を持った受験生同士が相互作用をもたらし、思ってもみなかった能力が育成されるのも特徴だ。

③「将来未定型」というまったく新しい総合型選抜:モヤモヤ入試*短大部のポリシー入試
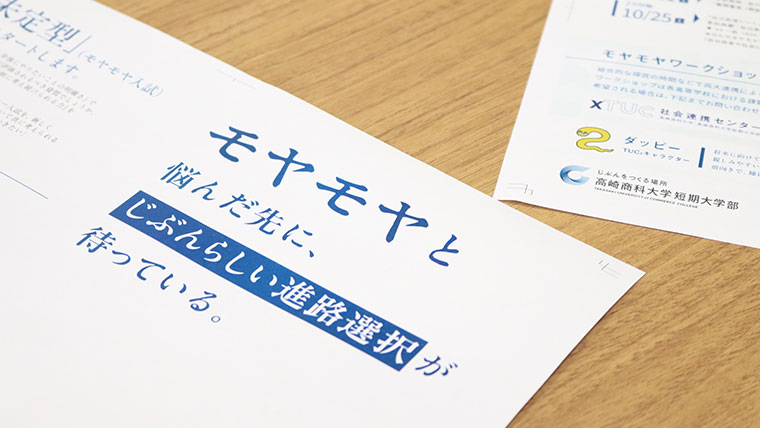
様々な入試改革の中で他に例を見ないのは短大部に新設された総合型選抜(将来未定型)通称:モヤモヤ入試だ。
一般的には大学進学を目指す受験生は将来の方向性を定めていることを前提としているが、現実には将来自分がしたいことが定まらず、モヤモヤした気分で進学を決定しなければならない人も多く存在するだろう。この入試のコンセプトは「将来について悩み続けることは悪いことではない。むしろ一生懸命自分自身を考えることはすばらしいこと」として、自分の未来を考え続けていくことを評価するという、入試形態としては今までにない発想から設置された。
本入試導入に際し、企画した鈴木氏は「この入試は一線で活躍する株式会社電通のクリエーターの皆さんとのコラボレーションから生まれました。何かにモヤモヤするということは、その事柄がどうでもいいことではなく、気になっているということ。そこには、若者の好奇心や興味が隠れているのかもしれません。また、早急に稚拙な答えを出すのではなく、深く考えた先の答えはより本質的なものになりやすい。課題や答えが設定されていて、そこにたどり着く近道を覚えるだけの教育に一石を投じる意味合いもあるように感じています。」と語り、更に以下のように続けた。
「これまでの教育では、『社会に役立つ人材育成」のため、早急に問題解決できる能力の育成が求められていたように思います。しかし、VUCA(注)と言われる変化の激しい時代には、目先の問題を解決するのではなく、より深く洞察することも大切でしょう。将来を決められない受験生の中には、たくさんの選択肢の中を彷徨い歩いている人もいるでしょう。そんなモヤモヤを短大で一緒に共有したいと思っています。」
(注)VUCA
Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の頭文字からなり、社会・ビジネスで未来の予測が難しくなる状況のことをあらわす。
試験内容は書類審査と筆記試験のほか、この入試ならではの課題である「自己表現シート(モヤモヤシート)」の作成と、これを基にした面接が行われる。受験生は、今抱えているモヤモヤ、例えば自分自身や社会に対しての望みや悩み、興味や不安、疑問、提案、理想、意思などを表現することとなる。入学後もキャリアプランニングやオートノミープログラム(自立支援の授業)で学び続けるので、入試の課題が授業課題のようにさえ感じられる。卒業後の進路は就職、4年制大学編入、留学など多方向の道があることがこの短大の特徴でもあり、2年間の学びの中で学生は自身が求める方向性の精度を高めることもできる。4年制大学よりも早期の2年後に進路選択のタイミングがやってくる短大にマッチした入試制度とも言えよう。なお、本入試制度を基に、「モヤモヤワークショップ」と銘打った高大連携授業も考案し、公募する予定とのことであった。
④多様な生徒を評価する二つの新しい学校推薦型選抜(大学・短大)
TUCは前述の簿記会計型学校選抜制度の他にも新しい学校推薦型選抜を導入する。
一つは「数理・データサイエンス活用制選抜」。「情報」や「数学」の学習を重視した入試制度だ。具体的には「基本情報技術者試験」「応用情報技術者試験」「ITパスポート試験」「実用数学技能検定2級」のいずれかに合格していることが必須で、これに書類審査、面接、筆記試験を課して総合的に判定する。簿記会計活用制選抜と同様、各分野で努力した生徒を評価する選抜制度としての導入なのだが、TUCは2年後に情報系学部開設の構想がある。文理の分け隔てをせずに今後は数学と情報の教育環境を伸長していくという、大学としての意思の表れでもある。
もう一つは「全国児童養護施設推薦制選抜」だ。これは児童養護施設に入所している高校生に対して、施設長推薦のもとで出願できる制度である。学費免除制度もあわせて実施される。試験内容は公募制推薦と同内容で、出願時に1000字の志望理由書を提出する。TUC建学の精神「自主・自立」にのっとり、学業のみならず様々な環境で頑張った人、努力した人で、入学後もさらに成長していきたいという学生を評価するTUCの姿勢といえるだろう。
社会で活躍できる人材は一面的な特性では推し量ることはできない。大学で学び合う学生も多種多様であるべきで、その尺度の根本となる入試改革は重要度を増していくのは間違いない。TUCの入試改革は地域社会の発展を見越した先駆的な改革と言えるだろう。


