新型コロナウイルスによるパンデミックは、オンライン授業など教育DX(デジタル技術による変革)を推し進める一方、「大学で学ぶとはどういうことか」を再考する契機となりました。〈知〉の世界との出会いからこれからの大学のあり方、次代を担う若い人たちへの提言まで、東京大学第31代総長の藤井輝夫先生にお伺いしました。
(大学通信『卓越する大学 2023年度版』[2022年9月30日刊]より)
![[東京大学]多様な人々を「対話」でつなぐ ~藤井輝夫総長インタビュー [東京大学]多様な人々を「対話」でつなぐ ~藤井輝夫総長インタビュー](https://univ-online.com/wp-content/uploads/image/jpeg/24217/IMG_9005.jpg)
東京大学 藤井 輝夫総長
- 1964年生まれ。1988年東京大学工学部卒業、93年同大学院工学系研究科博士課程修了。理化学研究所勤務を経て、2007年東京大学生産技術研究所教授。その後東京大学生産技術研究所長、同大学執行役・副学長、同理事・副学長、同社会連携本部長などを経て、21年4月東京大学第31代総長に就任。専門分野は応用マイクロ流体システム、海中工学。
──藤井先生は当時5歳だった1969年、アポロ11号が人類初の月着陸に成功したことがきっかけで、エンジニアの道に興味を持たれました。
当時のことは強く印象に残っています。不思議なことに、月そのものに対する興味よりも、「人類が自ら創り出したテクノロジーで月に行けるようになったこと」に感動しました。
──科学技術に対する感性が鋭かった。
科学に限らず、興味の幅は広かったですね。図鑑もたくさん読んでいましたし、そういえば、子どもの頃からいろいろな施設に突撃取材のようなことをしていました。例えば、電話局の中がどうなっているのか知りたくなって、「ちょっと見学させてください」と電話をかけて交渉するなどしていました。
──それもある意味、社会の構造、メカニズムへの興味ですね。
当時有楽町にあった都庁や、企業の工場なども見学させてもらいました。友人を誘って一緒に行くなど、放課後の遊びの感覚だったと思います。
──とても行動力のある小学生でしたね。その後、先生は港区にある麻布中学に進まれます。全国屈指の進学校ですが、自由な校風でも知られます。
中学では水泳部に入って、主将も務めました。中学2年生の頃からはロックやフュージョン系のバンド活動も始めました。当時、AMH(Azabu Music House)というサークルがあり、そこで先輩に交ざって演奏したり、コンサートを開いたりして中高時代を過ごしていました。
麻布は文化祭や運動会も盛んで、みんな自由に楽しんでいました。今思えば、自分が興味を持っていることに努力を惜しまず、目一杯打ち込むのは大切なことだ、ということを教えられた中高時代でしたね。
海中ロボットから
マイクロフルイディクス (Microfluidics) へ
未踏の技術をめぐる冒険
──高校卒業後は、東京大学理科一類に進学されます。
大学でどんな分野に進もうかと考えたとき、宇宙にももちろん興味がありましたが、海に関する分野が面白そうだなと思いました。特に海の中はいったいどうなっているんだろうと思うようになりました。バチスカーフ・トリエステ(深海探査艇)がマリアナ海溝に潜ったことは科学雑誌で知っていましたが、深海の世界は依然として未踏の地でしたから、海中を探索する技術を自分の手で開発してみたいと考えました。それでいろいろと調べた結果、船舶工学科(当時)があり、海洋研究所(現:大気海洋研究所)もある東大に進むことにしたのです。
──大学院では海中ロボットの研究に取り組まれました。
今では水中ドローンとも呼ばれますが、当時、海中ロボット(自律型無人潜水機)は新しい技術で、博士課程が終わった後も、東大の生産技術研究所の寄付研究部門(いわゆる寄付講座)の教員として海中ロボットの研究を続けていました。
しかし、寄付研究部門には年限があり、継続されずに終わってしまうことになりました。いろいろな研究職に応募した結果、理化学研究所(理研)の中でもまだ新しいポスドク制度であった基礎科学特別研究員に採用されました。そこで原子力用ロボットの研究に取り組み始めるのですが、主任研究員だった遠藤勲先生に「せっかくうちに来たんだから、何か新しいことを始めなさい」と勧められて……。
──新たな挑戦が始まる。
ちょうどその頃、私には海中ロボットとともに、もう一つ興味のあるストーリーがありました。それはいわゆるマイクロマシン、一般にMicro Electro Mechanical Systems (MEMS)といいますが、半導体の微細加工技術を使って微小な機械をつくる、という世界的にも立ち上がりつつある研究でした。恐らく今の高校生のみなさんはご存じないかもしれませんが、『ミクロの決死圏』という……。
──医療チームがミクロの潜水艇で体内に潜り治療を行う、1966年公開のアメリカのSF映画ですね。
そういうのができたら面白いな、と漠然と考えていたのです。東大の生産技術研究所時代に、MEMSについて活発に研究しているグループのリーダーだった藤田博之先生に、研究会のような形でいろいろと教えていただいていたバックグラウンドがあったので、マイクロマシンに対する関心はありました。ただ、微小な機械で物理的な動作を行っても、大きなエフェクト(効果)を得ることは難しい。ミクロな機械だと、この手のひらを移動するだけでも相当大変なことだからです。
それならば、バイオケミストリー的な発想で、極めて微小な入れ物の中でさまざまな化学反応をさせ、その結果を調べる。そんな研究を可能とするようなミクロの容器を開発してはどうか、ということに思い至りました。
タンパク質の合成は生合成といって、細胞につくらせるのが一般的ですが、理研では東大の教授も務めておられた横山茂之先生が、細胞を使わずリアクター(反応装置)でタンパク質をつくる研究をしておられました。
もしミクロの反応容器の中で外から特定のDNAを入れ、そのDNAの遺伝子がコードしているタンパク質が合成できるようになると、それは細胞のようなものをつくっていることになるのではないか。これは面白いということで、ミクロの反応容器である「マイクロ流体デバイス(Microfluidic Devices)を創る研究に取り組むことになりました。
──生命の創出に関わるような……。
いわゆる人工生命(Artificial Life)という概念は、数学的な計算やシミュレーションの中から出てきたもので、当時盛り上がりを見せていました。人工細胞に関する議論もよくしていましたね。
──まさに未来の生命科学に関わる、最先端の技術ですね。
これら一連の研究は、私の専門であるマイクロフルイディクス(Microfluidics)という分野に結実します。そこで使うマイクロ流体デバイスは、液体を扱うことのできるデバイスです。タンパク質合成のような生化学も扱えるし、デバイスの中で細胞を培養することもできますから、例えばヒトの体内に近い条件でいろいろな臓器由来の細胞を培養し、薬の効き目を調べるなどすれば、創薬分野でも活用することができます。
──マイクロフルイディクスの応用範囲はとても広いのですね。その無限の可能性を求めて、世界中の技術者たちが研究にしのぎを削っていたと。
海中ロボットもそうですが、新しい分野を始めるときというのは、だいたい世界でどの人が何をやっているか、お互いに分かっているものです。エンジニアリングの世界では、その分野自体を発展させていくため、技術の可能性をみんなで共有して、より面白い、新しいアイデアを互いに提案し合う、ということがとても楽しいのです。
──一方で、自分がいま追究している研究は果たして正解なのだろうか、といった孤独な部分はありませんか。
そういう孤独を感じたことは、あまりないですね。何かを可能にしようと思って取り組む、その方法は決して一通りではないのです。エンジニアリングの場合は、その人ごとにソリューションがある。自分の工夫、アイデア次第で、実際に結果を得ることができるわけです。それを研究の仲間同士で伝え合う。そんなイメージですね。
──なるほど。解は一つではないということですね。受験勉強では、一つしかない解をどうやって見つけるかということに挑むわけですが、最先端の研究の世界では、いくつもある解を自分で見つけていくという。
解を見つけていくというよりは、むしろ自分の興味に従って問いを探していくことが重要です。これを実現するためにはどうしたらよいのだろう、と試行錯誤を重ねていくことが研究なのです。
![[東京大学]多様な人々を「対話」でつなぐ ~藤井輝夫総長インタビュー [東京大学]多様な人々を「対話」でつなぐ ~藤井輝夫総長インタビュー](https://univ-online.com/wp-content/uploads/image/jpeg/24217/80eee48db23c71ad382ad343802dc03f.jpg)
多様性に開かれた「対話」を通じ
社会とともに未来を創る
──藤井先生は、東京大学の第31代総長に就任された際に、UTokyo Compass「多様性の海へ:対話が創造する未来」という、東京大学が目指すべき理念や方向性をめぐる基本方針を示されました。これから東大はどのように変わっていくのでしょうか。
東京大学は非常に多様な分野で先生方がそれぞれの学問を深く究め、それがすぐれた「知」を生み出しています。私がもともと所属していた生産技術研究所では、大学の外部、すなわち地域や産業界、そして世界とも近い距離感で研究に取り組んできました。大学は素晴らしい知的資産をたくさん産み出しているので、それらをもっと外に伝えていくべきですし、社会の中でももっと大学の知を活用していただくべきだと思います。
世界に目を向けると、人類社会全体にとって危機的な出来事がたくさん起こっています。気候変動や新型コロナウイルスによるパンデミックもそうですし、理不尽な軍事侵攻まで起こってしまった。それに対して私たちはどのように、解決への手がかりを導き出していけばよいか。ただ大学の中に閉じこもって研究だけをしていればいいということではなく、外の世界の人々と一緒に考え、行動することが大事だろうと思っています。
その意味で、UTokyo Compassでも、「対話」を大切な実践と位置付けています。さまざまな人々を受け入れ、多様な背景を持つ人々が集まって知恵を出し合う。大学をそのような場にしていきたい。
今年(2022年)の入学式の式辞で、私は「起業」について話をしました。高校生の皆さんも、大学に入学すると視界が大きく開けると思います。社会のさまざまな声も耳に入って来る。大学の外での活動の機会も増えますし、社会に直接触れることになる。学内の活動はもちろん大事ですが、学外でのいろいろな経験をぜひ積み重ねてほしい。起業というのは、それを実現する、一つの形態でもあるわけですね。
──世界でも、既存の枠に縛られないスタートアップ企業のスピード感と実現力には大きな期待が寄せられていると、藤井先生は式辞で述べられました。一方で、「日本社会には挫折や再起に対して冷淡である」というナラティブ(物語)がある、とも指摘されています。
だからこそ、可能であれば在学中に挑戦してみて、ダメならもう一度チャレンジしてもいいし、NPOのような形式も含めていろいろな方法があるわけですから、違う道を選んでもいい。そのように、起業を広く捉えてほしいと思っています。
「起業とは、社会に潜在的に存在するさまざまなニーズ(必要性)やウォンツ(欲求)を見いだし、それに応える商品やサービスを創り出すことだ」と、入学式ではお話ししましたが、起業やビジネスの本質は、実は「ケア(顧慮)」という、もう一つの言葉が指し示す領域とも深くつながっています。
社会の役に立つこと、困っている人たちを助けるために頑張ることが「起業」だとすると、例えビジネスとしては失敗したとしても、その後のキャリアの上では貴重な経験になるはずです。
──藤井先生は、「想像力を働かせ他者をケアすることは自分の生を拡張することにもつながっている」とも述べられました。時には挫折することもあるかもしれないけれど、学生たちがいろんなことに思い切ってチャレンジする、そんな姿勢を受け入れる風土を社会の方でもつくらなければなりませんね。大学での4年間など、あっという間に過ぎ去ってしまうのですから。
私はちょうど10年前、総長補佐だった時に、入学したばかりの学部学生が自ら申請して、1年間の特別休学期間を取得し、本学以外の場でボランティア活動や就業体験、国際交流などの社会体験活動を行い、自らを成長させる「FLY Program(初年次長期自主活動プログラム)」をつくりました。「プログラム」といっても、大学が学習メニューをつくって提供するものではなく、その内容は学生自身の主体性に基づいて立案されます。審査の上、採用された学生には経費の一部もサポートするもので、2022年度は8期生の募集を再開しました。私自身は、学生がみんな同時に大学に入学して、同時に卒業し、同時に就職するという従来のスタイルのままでいいのだろうか、それぞれに時間的な多様性があってもいいのではないか、ということをこの10年間、ずっと考えてきています。
──社会に占める大学の役割が大きくなりつつある中、新しい時代の大学のあり方を模索し、提示する東京大学の挑戦にますます目が離せません。
最後に、受験生にメッセージをお願いします。
何よりも大切なことは、自分の真に興味のあることを突き詰め、没頭することです。大学に入ると、さまざまな制限がなくなり社会に開かれますし、場合によっては世界にも開かれます。自分の居場所を変えることもできます。世界に存在する、さまざまな可能性を持つ多様な人たちとともに、ぜひ広い視野を持って、自分の興味の向く方向に積極的に進んでください。私たちも、それをできるだけ後押しするような大学でありたいと思います。
――ありがとうございました。
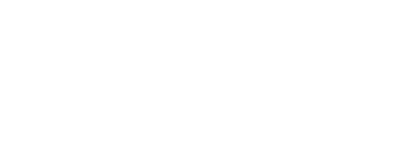

![[東京大学]多様な人々を「対話」でつなぐ ~藤井輝夫総長インタビュー](https://univ-online.com/wp-content/uploads/image/jpeg/24217/IMG_9073-760x428.jpg)